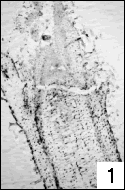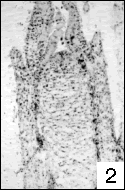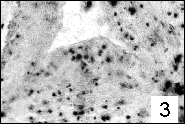|
私たちは、10年以上の間、cRNAプローブを用いたドットブロットハイブリダイゼーションやPCR、PCR-ハイブリダイゼーションなどの手法を用いてキクわい化ウイロイド(CSVd)の検査を行ってきたが、検出感度の低さ、疑似陽性反応、植物組織が持つ阻害物質などに悩まされていた。 LAMP法の導入により、明らかに研究内容は次のステージに進むことができた。PCR法に比較して明らかに高感度で迅速、安価なリアルタイムシステムである。さらに、PrimerExplorerを用いれば、新たなウイルス・ウイロイドのプライマーを設計することも容易である。 しかし、同時に今まで潜在していた問題も鮮明に浮き上がってきた。植物の体内では病原体との争いがあるのか、日々濃度が変化しているようである。植物組織内の多糖類、ポリフェノールは、低濃度の病原体の検出を著しく阻害する。少し高い次元ではあるが、PCR法を行っていた時と同様に「本当に感染しているのか?薄いのか?検出できていないだけなのか?」といった悩みを再び抱えることになった。 また、植物では、「フリー化」といわれる作業も頻繁に行われる。ウイルスやウイロイドに感染していても、頂端の分裂組織付近に向けて、「求頂的に」病原体の濃度が薄くなるとされているために、この分裂組織だけを切り取って in vitroで再生させて病害に感染していない植物、いわゆるウイルスフリー植物を育成することは商業的に行われている。だが、キクにおいてCSVdのフリー化は非常に困難とされており、成功例も少ない。 なかなか「フリー化」できないキク、LAMP法による検定でも不安定な低濃度感染個体など依然として困難な壁は存在する。CSVdは、植物の組織のどこかに隠れているのではないか?といった疑問がわいてくる。 植物組織のどこにCSVdがいるのかを突き止めるには、組織を薄い切片にし、ハイブリダイゼーションか遺伝子増幅で特定することになる。組織内(in situ)でハイブリダイゼーションすることを、in situ hybridization といい盛んに研究に使われているが、in situ PCR はそれほど行われていない。増幅産物のちらばりが問題となるそうである。PCR法の増幅産物は断片であるが、LAMP法の増幅産物はつながって絡み合っている、ちらばりにくいのではないかとも思える。 in situ LAMP を行う際の精神的なハードルは切片作成である。パラフィン切片作成の煩雑さを考えるだけで躊躇してしまう。簡便な凍結切片で薄く切ることができれば問題ないが、植物の場合50μm以下できれいに切るのはなかなか難しい。しかし、鶴見大学歯学部 川本忠文先生が開発した「粘着フィルム法」を用いると、植物組織でも凍結切片を10μm以下の厚さで簡単に作成することができる。まさにブレイクスルーと呼ぶにふさわしい技術である。 in situ LAMP の開発にあたっては、栄研化学株式会社の森 安義先生よりアドバイスをいただき、Bst DNA polymerase がdUTPの取り込み効率が良くないことからインナープライマーをDIG化して使用することとした。 この2つの技術、すなわち粘着フィルム法による凍結切片作成およびin situ RT-LAMP法を用いることで、これまで非常に煩雑で長期間を要した植物組織内での遺伝子発現は、迅速かつ高感度に行うことができ、サンプリングから切片作成、in situ RT-LAMPおよび染色までの一連の操作を8時間で行うことが可能だった。軽度のCSVd感染株でさえ先端の分裂組織(シュート頂)内部にCSVdが入り込んでいることが明らかとなった。
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||